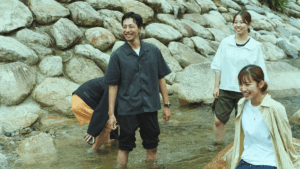ーーー 現在、どういった事業を展開されていますか?
東京と東北を中心に、約35名のメンバーと一緒に「デザイン」という概念を広く捉え、多岐にわたる事業を展開しています。具体的に言えば、Webや映像など広告制作はもちろんなのですが、経営者インタビューやワークショップを行った上での企業理念の整理や、ブランド立ち上げや新商品開発のサポート、新卒向け企業研修など人事関連の業務や、まちづくり支援、商店街の指針をつくるという仕事もあります。アウトプットそのものをつくるだけではなく、そこに至る過程を含めて提案させていただくことが多いです。
目指しているのは「本質的な価値観を捉え、伝える」ことで、それに必要な手法としてデザインを活用しているという位置付けです。例えば、株式会社アダストリアのライフスタイルブランド「LAKOLE(ラコレ)」のクリエイティブディレクションは「あたりまえを、素敵に。」というタグラインから考えたのですが、身の回りにあたりまえにある日常着や雑貨一つひとつを、少しずつ素敵にしていこうというブランドの価値観を伝えるために、映像やWeb、店舗看板などをデザインするという順番で考えています。Columbiaのバックパック開発も、アウトドア技術は休日用のものではなく通勤時にも活用できるという価値観を。銀座の商業施設「SALON 91°(サロン・ナインティワン)」は、銀座という都心だからこそ本音で過ごす時間が必要という価値観を伝えるといった具合です。それを伝えるために、ストーリーやアウトプットを考えてプロデュースすることで、企業やブランドの本来の価値を引き出し、高められることを目指しています。
ーーー 事業を始めたきっかけと、現在までの歩みについて教えてください。
Apple社のスティーブ・ジョブズへの憧れが関係しています。例えば、iPodは単なる高音質の音楽プレーヤーではなく、ポケットに何万曲も入れて持ち運べることによって、音楽という価値観を変えたと思うんです。ジョブズの可能性を広げたいというイノベーションの精神に感銘を受けました。弊社社名であるスティーブアスタリスクの「スティーブ」は僕のジョブズへの憧れそのものですが、「アスタリスク(*)」はプログラム言語でかけ算の意味もあり、既存の価値観に新たな可能性をかけ合わせるような仕事をしていきたいという思いが込められています。
1996年に東北学院大学経済学部に入学して専攻していた情報経済論に興味を持ち、当時普及し始めたインターネットが世の中にどのような変化をもたらすかについて研究していたのですが、何が変化するかではなく何もかもが変わるぞと感じて、研究に没頭していました。その後、当時衝撃を受けた映画「マトリックス」からの影響もあり、キアヌ・リーブスが演じていた主人公、トーマス・アンダーソンがシステムエンジニア(SE)という職種だったことをきっかけに興味を持つようになり、プログラムによって世の中の色々なものを作りたいと思うようになりました。
おかげさまで無事にシステムエンジニアとして大手企業に就職できたのですが、何か違うと感じていている時に「Webデザイン」という概念が突然現れました。当時、デザインを仕事にするという感覚は全く無く、システム構築を仕事ながら給料をもらって趣味でデザインの本を買うという生活が自分の生き方だと思っていました。でも、急激にWebデザインというものが世の中に広がってきたタイミングで、システムとデザイン両方に興味がある人間があまりいないということを知り、ここにいるよ!って伝えなきゃと思ったんです。24歳で上京し、そこから本格的にデザインの現場に入っていった感じです。今考えれば無謀ですよね。
ーーー 現在向き合っている社会課題について教えてください。
私たちが大切にしているのは「リアルな日々に関わりたい」という想い。デザインやクリエイティブと言うと、どこかテレビの向こう側の遠い世界のような、現実世界からは離れた虚像のことと思われることもあります。実際、デザインの現場で美しい世界を描いているアートディレクターやコピーライターが、現実の生活ではまったくその商品との接点が無いという矛盾も多くあることでしょう。でも、僕らはリアルを大事にしたい。日々の生活をもっと良くしたいという強い思いがあります。
生まれ故郷の宮城県丸森町では町の公式クリエイティブディレクターとしても活動しており、職員向けのデザイン思考研修や、広報誌への連載やシティプロモーションの企画などを継続的に行っています。自分が暮らしている町に仕事で関わらせていただきながら、変化をリアルに感じる日々は、本当にありがたい経験だなと感じています。先日は、年に一回の弊社の研修旅行で丸森町のキャンプ場に全員で集まったのですが、やっぱりリアルに顔を合わせて語り合うって大事だなと改めて感じました。(写真はその時に撮影したもの)
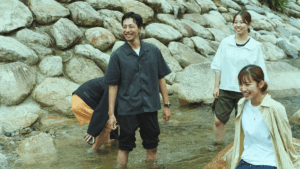

デザインやクリエイティブは単なる表現手段ではなく「価値観を変える総合的な力」だと考えています。だからこそ、もっとリアルな企業の未来づくりや地域社会の課題解決にこそ活かしていくべきだと強く感じています。最近では、私自身も東北に生活の拠点を移し、地域に根付いた資源や人の力を活かしたプロジェクトを中心に動いています。仙台市では市庁舎建て替えプロジェクトの公民連携検討委員として参画。2022年からは山形県山形市にある山形市第一小学校の旧校舎をリノベーションした施設、やまがたクリエイティブシティセンターQ1(キューイチ)に、東北初の拠点として「Steve* CREATIVE LOUNGE(スティーブ・クリエイティブラウンジ)」を開設しています。ここは、自然発生的に生まれる出会いやコミュニティから、新しいものを生み出す拠点となっていて、東北から様々なアイデアを生み出す場所として活用されています。今後も、様々な人が集い、一緒にコーヒーやお酒を飲みながら「それいいね!」という発言が飛び交う場になってくれれば、東北から世界に発信できる、新たなものがたくさん生まれていくと思っています。
ーーー 今後の展望についてぜひ聞かせてください。
様々な業界に関わる中で、自身の仕事がデザインそのものの専門家ではなく、各業界の可能性を広げるために活動したいと考えるようになりました。これまでの経験を生かし、今後も東北の可能性や価値観を広げるための、クリエイティブの土壌をつくりたいと思っています。特に、教育の現場で「失敗を恐れない」という姿勢を伝えていきたいです。僕自身も数多くの試行錯誤を重ねてきましたが、その一つひとつが成長の糧になっています。若い世代を含め、誰もが挑戦できる環境をつくることが大切です。東北学院大学や東北芸術工科大学で講師として授業を行ったりもしてきましたが、もっと早い段階、高校生や中学生、小学生のうちからデザイン教育を取り入れていくことで、「変化に強い、しなやかな思考」を育てていきたいです。何が起きるかわからない時代だからこそ、何が起きても対応しようとする力が求められていると感じています。
ーーー ご自身は東北学院大学に在学中はどんな学生でしたか?
時間的余裕は無限にありましたが、お金は全くなかったです。今になって考えると、時間的な自由を活かして、様々なことへの興味を育てる時期だったと思っています。また、学生時代に様々なアルバイトを経験したのも良い経験になりました。駐車場の警備員、コンサートスタッフ、工場での夜勤、中華レストランのスタッフなど、多種多様な仕事を経験し、たくさんの価値観を得たことで、現在の仕事にも応用できる考え方の基礎ができたと感じています。よく、早いうちに将来の目標を決めた方が良いと言われたりしますが、18歳の頃に考えられる将来なんて限界がありますよね。大学生活のうちに、さまざまな社会と接することで気づくこと、見えることが大きかったなと思います。
また、大学卒業後の話ですが、24歳で東京に行ってから「東北の大切さ」に気づきました。それまでは意識せずに育った故郷への「郷土愛」や「帰る場所がある」という温かい感覚は、東京に出てから芽生えたものだと思っています。特に東日本大震災の際に、故郷への強い思いを再認識し、「何のために働くのか」といったことを深く考えるきっかけになりました。これも、東北学院大学での4年間で良い経験がたくさんできた期間だったからだと思っています。
ーーー 将来スタートアップを目指したい学生に対してのメッセージをお願いします。
先ほども言いましたが、「失敗を恐れない」ことを大切にしてほしいです。一度も失敗したことがない人というのは、一度も想像を超える新しいことにチャレンジしたことがない人です。“はじめて”のことに挑戦したいという気持ちは、人生をより楽しくするための才能だと思っています。クリエイティブの現場と同じように、新しい経験はゼロから学び、成長する機会を与えてくれます。「やれるかどうか」よりも、自分の気持ちに向き合って「やりたいかどうか」を優先してみてください。仮にその結果が失敗だったとしても、「プラスマイナスゼロ」より「プラス10、マイナス8」のように全体としてはプラス、という考え方の方がいいと僕は思っています。
さらに、自分で楽しむマインドを持つことも大切だと考えています。何かを始めるときに人から何を言われるかを気にして、自分の好きなことを諦めてしまうのは、とてももったいないことです。年齢に関係なく、常に「子どもの時の心」、純粋な好奇心と情熱を持ち続けていれば、良い出会いが重なっていく気がしています。僕がこれまで出会ってきた会社のメンバーも、そういう気持ちを持ち続けたおかげだと思っています。ぜひ、楽しみながら挑戦し続けてみてください。