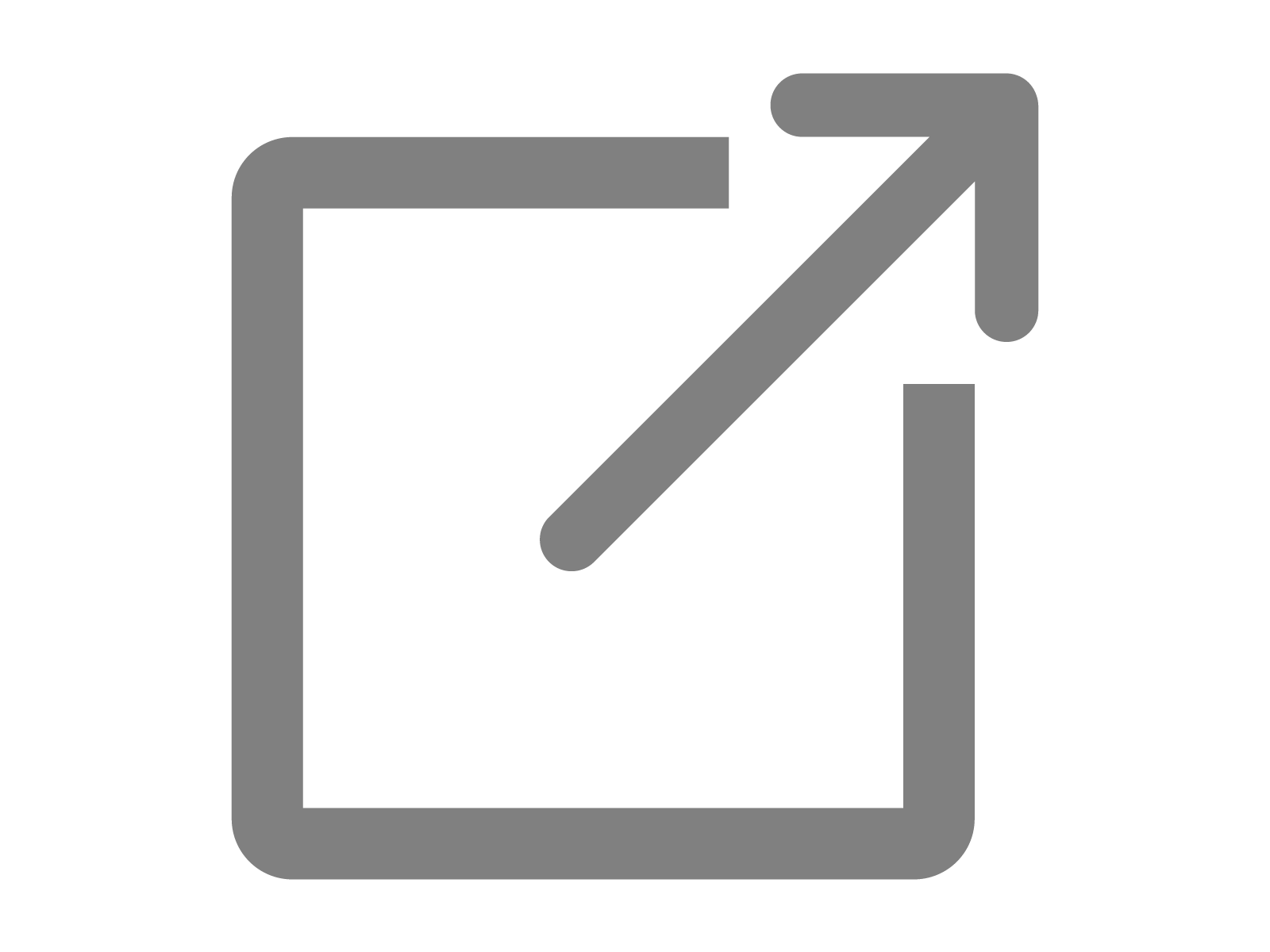ーーーまずはご自身の事業内容を教えてください。
はい、0歳0カ月から頼めるベビーシッターと家事代行の「Family Sitter 仙台」という事業を行っています。宮城県でも珍しい、生後0カ月から保育ができるベビーシッターと家事代行の両方を提供するサービスです。

子育て中や妊娠中の家庭に訪問し、料理や洗濯、掃除などの日常的な家事、赤ちゃんの保育や沐浴、上の子のお世話などを行います。生後0カ月から保育ができるサービス自体も珍しいのですが、ベビーシッターと家事代行を両方行うという点も、実は宮城ではなかなかない取り組みです。

核家族や親族が近くにいない子育て世帯の新たな頼り先として、地域からのニーズが高まっています。赤ちゃんを育児していると、1時間も家事ができないうちに細切れで赤ちゃんのお世話をしなければならず、家事が回らないご家庭がほとんどです。まだまだ男性が育児休暇を取れる会社も少ないため、お母さんに家事育児の負担が偏りやすく、子育ての孤独感や負担感が大きくなってしまう原因にもなっています。夫婦だけで子育てをしていたり、親族に頼れない方々の新たなサポート先として当社をご利用いただいています。親の家事負担を減らすことは、親子の時間を増すことに繋がります。2時間のサポートで料理を8品ほど作ると、とても驚かれますね。

これまでは、保育士や保育園勤務経験5年以上のベテラン保育士を中心に採用していましたが、最近は保育未経験者の採用も始めました。現在は、自社でプロのシッターを育成し派遣する体制を整えたので、今後は規模拡大のフェーズに入ります。
ベビーシッター業界では、安全対策で国の基準を100%満たしている事業所が全体の13%ほどしかないと言われていますが、当社のマニュアルはそれ以上に厳しい基準を設け、100%を満たしています。大切な子どもをお預かりする責任を果たせる基盤があるからこそ、スタッフの個性を活かし、多様なニーズに対応できると感じています。
 今後はさらにAIを活用し、ベビーシッターが書く日報から産後うつのリスク要因になりそうな言葉を拾い上げ、次の訪問者に向けたサポートのアドバイスを送れる仕組みも作りたいと思っています。うつの要因はやはり育児ストレスや疲労が大きいですから、お母さんやご家族が現在どんなことで困っているのか、何に悩んでいるのかを言語化し、社内で共有しています。それがしっかりとできれば、「次回はこうした方がいい」という具体的な支援内容を次の訪問担当者に申し送りできます。
今後はさらにAIを活用し、ベビーシッターが書く日報から産後うつのリスク要因になりそうな言葉を拾い上げ、次の訪問者に向けたサポートのアドバイスを送れる仕組みも作りたいと思っています。うつの要因はやはり育児ストレスや疲労が大きいですから、お母さんやご家族が現在どんなことで困っているのか、何に悩んでいるのかを言語化し、社内で共有しています。それがしっかりとできれば、「次回はこうした方がいい」という具体的な支援内容を次の訪問担当者に申し送りできます。
そういった理由から、ベビーシッターを採用する際にも、お客様の状況を客観的視点で言語化できる能力があるかを重視しています。また、お客様が何に悩んでいるのか、どうすれば最適なサポートができるかという判断は、文化的バックグラウンドが異なる外国人シッターを採用した場合、解釈や対応がずれるリスクがあるため、質を一定に保つうえでもAIを使って産後うつリスクにつながる言葉を拾い出すアプローチはとても有効だと思っています。
私たちは、人の手でしか提供できないあたたかいサポートを大切にし、子どもたちが日常的に過ごす環境に溶け込みながら、人とのコミュニケーションの楽しさが伝わる保育をしていきたいと考えています。また、子育て中の親が望む形で子育てを実現できるよう、下支えする役割も担っています。子どもの成長を一緒に喜び合ったり、長期的に家族に関わることで信頼関係を重ねていくことが理想です。何よりも、子育て中の親の気持ちを大切にできる伴走者でありたいと思っています。

ーーーこの事業を始めようと思ったきっかけを教えてください。
 きっかけは大きく二つあります。
きっかけは大きく二つあります。
一つ目は、私の母が産後うつを患い、私がまだ7歳のときに(妹出産時)亡くなったという背景があることです。その経験から、自分と同じように寂しい思いをする子どもを少しでも減らしたいという思いがありました。
二つ目は、私自身が出産した際、夫は気仙沼、私は丸森で暮らす“週末婚”状態で、夫の実家のある香川県まで行って出産したことです。日本では核家族の子育て世帯が約82%を占めており、親族に頼る出産は限界を迎えつつあると感じました。同時に、好きな街で生み育てるためには、医療だけではなく生活支援を担う専門家が必要だと思ったんです。そこで、自分自身が産後ケアの資格を取得し、個人事業主としてスタートしたのがはじまりです。私の場合は、まさに実体験が起業に直結した形です。
ーーーご自身は東北学院大学に在学中はどんな学生でしたか?
自他ともに認めざるを得ないほど、かなり目立つタイプだったと思います(笑)。それは大学生に限らず、中学生や高校生の頃もそうでした。部活ではキャプテンを務めていましたし、本気で全国大会を目指して努力するのが好きでしたね。大学時代はダンスサークル「Dance Factory’s」に所属し、他大学や他県にも友人の輪が広がりました。
家庭の事情で大変な部分もありましたが、一人暮らしが始まって「自分の意志で学べる環境」を手にした途端、解放感もあり、さらにいろいろチャレンジしたいという気持ちが強くなりました。1年生の時から長期インターンシップに参加し、4年間で3つのインターンシップを経験しました。
幼少期に母を亡くし、地域の人たちに育てられたという思いがあるので、当時は地元の秋田県鹿角市のまちづくりに貢献したいというのが10代の頃の夢でした。行政以外の形でまちづくりに携わる方法を学びたいと思い、1年生のときには会津若松市のまちづくりNPOでインターンをしました。2年生のときは議員の事務所、その後はまちづくりを行っている企業で2年間インターンを経験しました。
いろいろな角度から「まちづくりとは何か」を学んでいる最中、ちょうど1年生のときに東日本大震災が起きたこともあり、企業でのインターンと並行して震災復興のボランティアにも参加しました。当時は「六次産業化」が全国的なブームでしたが、どの地域でも「ジャムやクッキー、ドレッシングを作ってもなかなか売れない」という悩みをよく耳にしたんですね。そんな中で私の中に芽生えた答えが、「その地域に人が来る仕組みを作ることが、地方創生やまちづくりにとって大事なのではないか」という考えでした。そこから観光を軸に就職活動を行い、リクルートの『じゃらん』への就職につながりました。
ーーー東北学院大学在学中に学んだこと、あるいは経験して今に生きていることはありますか?
ありきたりかもしれませんが、たくさんの友達ができたことが一番の収穫だと思っています。社会に出ると、ビジネスの調子や環境の変化で人間関係が変わることもありますが、学生時代の友達との付き合いは変わりません。私がどんな立場になっても変わらずにつながり続けてくれる仲間がいるというのは、本当に大きな財産だと感じています。今でも子どもや夫を含め、家族ぐるみで仲良く付き合いが続いていますよ。
また、私は共生社会経済学科に所属していましたが、当時は新設されたばかりの学科で、阿部重樹先生(当時学科長)が学生の意見を取り入れながら学科の方針を進めている雰囲気がありました。誤解を恐れずに言えば、東北大のように尖った技術を持っているわけではないかもしれませんが、「今の社会がどうなっていて、これからどうすれば幸せなのか?」といった問いを、先生と一緒に考えていたように思います。
ーーー将来スタートアップを目指したい学生に向けて、メッセージをお願いします。
 私たちの地域には東日本大震災という大きな出来事があり、誰もがその歴史を認識していますが、「そこで暮らしている人たちがどんな気持ちで今の仙台を作り上げてきたのか」を踏まえたうえで、「これからどのような社会を目指したいのか」「子どもや孫の世代のためにどんな地域を残したいのか」といった時間軸をもって事業を考えることが、地域で長く事業を続けるポイントだと思います。
私たちの地域には東日本大震災という大きな出来事があり、誰もがその歴史を認識していますが、「そこで暮らしている人たちがどんな気持ちで今の仙台を作り上げてきたのか」を踏まえたうえで、「これからどのような社会を目指したいのか」「子どもや孫の世代のためにどんな地域を残したいのか」といった時間軸をもって事業を考えることが、地域で長く事業を続けるポイントだと思います。
また、地方都市には大きな利点があります。東京とは違って自然や考える時間が豊富で、起業するプレーヤーが少ない分、チャンスも多い。人とのつながりを大切にし、最初から大きな売り上げを狙わなくとも、コツコツとお客様のニーズに応えて喜ばれることを積み重ねていけると良いですね。社会を変えるというのは、そうした日々の地道な取り組みの積み重ねだと思います。
起業の醍醐味は、自分が描いたビジョンを実現するためにどんどん挑戦していけることです。単に働いてお金をもらうだけではなく、「何かを社会に残していく」ことにやりがいを感じる方は、ぜひチャレンジしてほしいと思います!




 今後はさらにAIを活用し、ベビーシッターが書く日報から産後うつのリスク要因になりそうな言葉を拾い上げ、次の訪問者に向けたサポートのアドバイスを送れる仕組みも作りたいと思っています。うつの要因はやはり育児ストレスや疲労が大きいですから、お母さんやご家族が現在どんなことで困っているのか、何に悩んでいるのかを言語化し、社内で共有しています。それがしっかりとできれば、「次回はこうした方がいい」という具体的な支援内容を次の訪問担当者に申し送りできます。
今後はさらにAIを活用し、ベビーシッターが書く日報から産後うつのリスク要因になりそうな言葉を拾い上げ、次の訪問者に向けたサポートのアドバイスを送れる仕組みも作りたいと思っています。うつの要因はやはり育児ストレスや疲労が大きいですから、お母さんやご家族が現在どんなことで困っているのか、何に悩んでいるのかを言語化し、社内で共有しています。それがしっかりとできれば、「次回はこうした方がいい」という具体的な支援内容を次の訪問担当者に申し送りできます。
 きっかけは大きく二つあります。
きっかけは大きく二つあります。 私たちの地域には東日本大震災という大きな出来事があり、誰もがその歴史を認識していますが、「そこで暮らしている人たちがどんな気持ちで今の仙台を作り上げてきたのか」を踏まえたうえで、「これからどのような社会を目指したいのか」「子どもや孫の世代のためにどんな地域を残したいのか」といった時間軸をもって事業を考えることが、地域で長く事業を続けるポイントだと思います。
私たちの地域には東日本大震災という大きな出来事があり、誰もがその歴史を認識していますが、「そこで暮らしている人たちがどんな気持ちで今の仙台を作り上げてきたのか」を踏まえたうえで、「これからどのような社会を目指したいのか」「子どもや孫の世代のためにどんな地域を残したいのか」といった時間軸をもって事業を考えることが、地域で長く事業を続けるポイントだと思います。