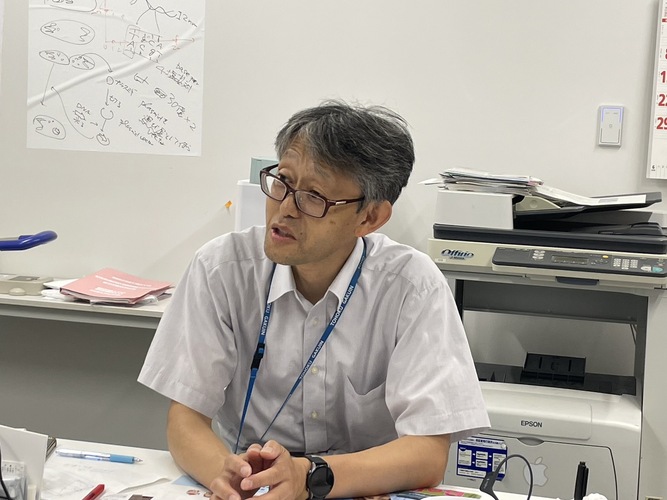ーーー研究室ではどのような研究をされていますか?
現在は、環境汚染浄化を可能にしうる生物の仕組みを解明する研究に注力しています。
特に、環境汚染物質の分解や無害化をおこなう微生物の働きを遺伝子・タンパク質レベルで研究しているのですが、現在の代表的なテーマはヒ素汚染対策です。ヒ素は自然界に存在する有害な金属で、地下水や土壌から人の体に取り込まれると、皮膚障害やがんなど深刻な健康被害を引き起こします。
南アジアなどでは地下水汚染が深刻で、日本でも環境基準値を上回る汚染が多く報告されています。宮城県では、東日本大震災による津波によって堆積した泥のヒ素濃度が高いということがわかり、それをきっかけにヒ素汚染浄化の研究を始めました。
ーーーこれまでの歩みについて教えてください。
もともとは埼玉で暮らし、その後東京大学に進学しました。さらに長岡技術科学大学で研究を深めた後、東北学院大学に移り、現在まで約19年間勤務しています。
微生物研究への興味は、中学校時代に起こったバイオブームがきっかけです。特にDNAの構造や細胞融合、農薬の分解といったテーマに触れたことで、生命科学や環境分野に強い関心を持ち、それが今の研究の出発点になっています。
現在は工学部に所属しています。工学部にいながら微生物研究をしていることに違和感をもつ方もいるかもしれませんが、下水処理分野では汚い水を浄化する際に微生物が利用されているなど、工学(土木工学)と微生物には元々関連があり、この接点から研究を広げていくことができました。
私たちの研究は、従来の土木工学的なアプローチとは異なり、微生物や植物がどのようにして有害物質を吸収・分解するのか、そのメカニズムを根本から理解することに主眼を置いています。工学が「実装」や「材料の応用」に重きを置くのに対し、私は「なぜその現象が起きるのか?」という生物の「仕組み」を明らかにすることを追求する、よりサイエンスに根ざしたアプローチを重視しています。興味を持てるテーマを追求し続けられたこと、そして人との縁に恵まれたことは、非常に幸運であったと感じています。
ーーー社会との接点となる取り組みにはどのようなものがありますか?
東北大学の研究室と共同で、シダ植物を用いたヒ素汚染土壌の浄化に取り組んでいます。特に「モエジマシダ」というヒ素を効率的に吸収する能力を持つシダ植物と、その根の周囲に生息する特定の微生物に着目し、実証実験を進めています。シダ植物には土壌や水中からヒ素を高濃度で取り込む性質がありますが、その際に根の周囲にいる微生物がヒ素を植物が吸収しやすい形に変換(酸化)する働きがあることがわかってきました。現在は、この微生物の働きをさらに詳しく解明し、彼らが最大限に機能できる環境を整えることで、より効率的かつ持続可能な土壌・水質の生物学的改良(バイオレメディエーション)の実現を目指しています。
また、世界に目を向けてみると東南アジアもヒ素汚染が課題となっています。現在、カンボジアで実証実験に取り組み、現地の地下水の水質改善に取り組んでいます。現地の地下水のヒ素濃度は高いため、飲料用には使われていません。この豊富な水資源を農業用水として利用できればメリットは大きく、現在は東北大学の研究室と協働で浄化装置を現地に設置して、試験的に運転をおこなっています。土壌や水質の改善は世界共通の課題であり我々の研究の成果がその解決に寄与できると信じています。
ーーー今後、どのようなビジョンを描いていますか?
ヒ素高蓄積植物の特性をもっと伸ばす助けをする「微生物」を明らかにしていきたいと考えています。そのために、吸収を助ける微生物のメカニズムをさらに深く解明し、これらの微生物が最も効果的に機能する環境を整える技術を確立することを目指しています。
ただし、社会実装には多くの課題があります。とくに、研究を通じて吸着・沈殿させた有害物質の最終的な処分方法は大きな問題です。焼却による再汚染リスクもあり、安全かつ持続可能な処理技術が急務です。産業廃棄物として処理するだけでは根本解決にならないため、例えば、回収した物質を安全に閉じ込める技術を開発することで、環境中への再放出を防ぎ、持続可能な形で問題を解決することを目指しています。
さらに、現在進めているカンボジアなど海外でのヒ素汚染対策への応用も重要なテーマです。これらの地域で継続的にヒ素汚染対策が進むよう、「メンテナンスフリー」に近い簡易なシステムを目指し、地域の人々が自立して環境問題を解決できるような実用的なソリューションを提供したいと考えています。
微生物の可能性は大きく、持続可能な社会づくりに貢献できると確信しています。最終的には、環境問題というネガティブなイメージを持たれがちな分野から、様々な可能性を引き出し、社会に貢献できるポジティブな価値を創出することを目指しています。今後は土壌中の微生物の働きをより深く解明し、土壌や水の浄化を通じて、より安全で持続可能な社会づくりに貢献していくことが、この研究の大きなビジョンです。
ーーー最後に、未来の挑戦者である若者たちに向けたメッセージをお願いします。
若い人に伝えたいのは「時間の使い方について」です。現代はタイパ・コスパなどの言葉が多く、効率やスピードが重視されがちで、学生もすぐに答えを求めがちだと感じています。しかし、人間という生き物の性質は根本的には変わっていません。現代社会のスピード感に流されず、もっと時間をかけて物事に取り組むことに注力してほしいです。
また、研究においてはプロセスにこそ喜びや感動があります。ネットで簡単に答えが得られる時代だからこそ、自分の手で試行錯誤し、まだ誰も知らない真実にたどり着く達成感を味わってほしいと思います。考えることに時間がかかることを恐れずに、じっくり時間をかけて考えを深めてほしいですね。
また、微生物のように未解明な世界に挑むことは、知的探求心を強く刺激してくれます。失敗を恐れずに挑戦する「アントレプレナーシップ」の考え方は、研究にも不可欠な精神です。焦らず、一つひとつのプロセスに丁寧に向き合い、自分だけの「感動」を見つけてください。
それが未来を切り拓く力になると信じています。