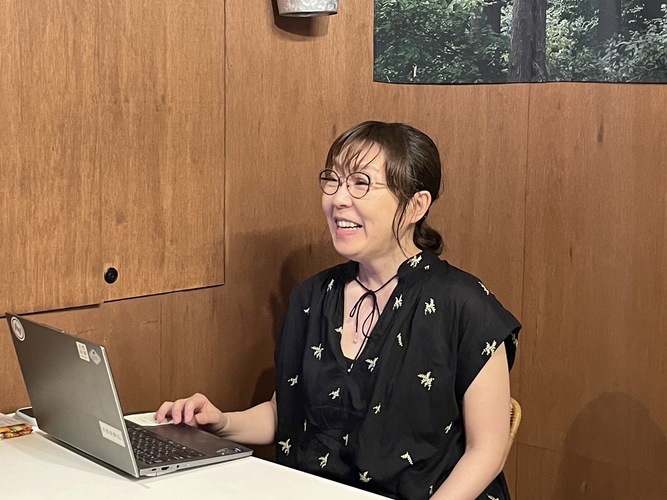ーーー 現在、どういった事業を展開されていますか?
「街を、人を、香りで幸せに」というコンセプトのもと、大きく二つの柱で事業を展開しています。
1つ目は、私たち自身のブランド『天然回帰(てんねんかいき)』の展開です。宮城や東北の自然素材を活かし、それらをアップサイクルする形でアロマディフューザーやスプレーなどの商品を開発しています。
2つ目は、香りを活用して企業のブランディングをお手伝いするOEM事業です。企業オリジナルの香り商品を企画・提案・製造し、ブランド価値の向上に寄与することを目的としています。
香りを通して地域資源の価値を再発見し、持続可能な形で届けることを目指しています。
また、一般社団法人ワンエムイノベーションにて、女性のエンパワーメントを推進する活動を並行して行っています。ここでは、「地方における女性の働き方やライフステージにおける課題」に焦点を当て、女性が現状から1㎜でも変化を生み出すためのスキルとマインドを醸成することを目指しています。
ーーー 事業を始めたきっかけと、現在までの歩みについて教えてください。
前職は、女性下着メーカー「ピーチ・ジョン」に17年間勤務していました。香りに興味を持ったきっかけは、前職時代に化粧品の企画を担当していたことです。香りのよい化粧品を作ったり、通販でお客様に商品を届ける際にサシェ(香り袋)を同梱したりと、香りを使ってブランドや体験に付加価値を与えることを自然と意識していたのだと思います。
起業のきっかけとなったのは、ホテルメトロポリタン仙台イースト様のエントランスの香りブランディングです。前職を辞めた直後、ちょうどホテルの開業にあわせて「ホテルオリジナルの香りを作れませんか?」とご相談をいただきました。当時はまだ法人化もしておらず、個人事業主という形でもなかったのですが、もともと前職でマーケティングや製品開発を担当していた経験が評価され、案件が決まりました。そして、ホテルのコンセプトが「東北六感 SENSE OF TOHOKU」で東北を代表するホテルを目指していたので、そのコンセプトを表現する香りをご提案しました。提案いただき、お取引を始める際に「法人のほうが取引しやすい」と言われたこともあり、法人化しました。計画的な起業というよりは、まさにご縁からスタートした形です。
その後、少しずつ事業が広がっていきましたが、起業してから1〜2年はまだ自分の軸も定まっていなくて、国際女性デーにイベント主催したり、オイル美容に関するライターをうやったり、大手コールセンターの品質に関するコンサルをしたり、やれることを色々やっていた感じです。
そこから今の形に繋がる大きな転機として、石巻市雄勝町(おがつちょう)にある「雄勝ローズファクトリーガーデン」との出会いがあります。起業して2〜3年目の頃に、知り合いのNPO団体から「企業の復興支援の一環で、新入社員研修受入のサポーターをやらないか」とお声がけいただきました。そこで雄勝ローズファクトリーガーデンの代表の徳水さんから「大切に育てたバラを何とか活用したい」と袋一杯のバラの花ビラを託されたという出来事がありました。
「私の経験が何かお役にたてれば」という想いから1本のスプレーを開発しました。翌年にはミントやラベンダーの素材を追加して『aroma journey (アロマジャーニー) 』というシリーズにリニューアルしました。この商品は「マスク&ルームスプレー」として販売をスタートした直後に、新型コロナウイルスの影響もあり、うちの看板商品になってくれました。その後、今後の事業の方向性や自分が感じている課題に向き合うために、仙台市が行う社会起業家支援プログラム「Social Impact Accelerator (SIA)」にも参加しました。プログラムの中で、秋保ワイナリー様と再会する機会があり、ワインの原料となるブドウのツルをアップサイクルしたリードディフューザーが誕生しました。

ありがたいご縁に恵まれながらも、事業としての課題もありました。当時の商品単価は1,000円代が中心で、リピートも少ないというアロマ雑貨としての限界も感じていました。コロナ後の事業展開を見据え、ユーザーが日常的に使い、リピートするものという方向性を定め、化粧品事業に舵を切ることに決めました。補助金やクラウドファンディングを活用しながら準備を進め、2024年7月に化粧品製造業・製造販売業の許可を取得、本格的に化粧品・アメニティ事業に取り組み始めました。
また、このタイミングで、すべてのブランドを『天然回帰』としてリブランドするという大きな決断をしました。ブランドコンセプトも見直し、全てのメッセージ、パッケージ、ビジュアルもリニューアル、どこで取り扱っていただいても、「天然回帰」としての認知を拡げていくことを目指し、商品の品揃えも見直しました。たとえ、売れ筋だった商品であっても、コンセプトから外れてしまうシリーズは、勇気をもって廃版するという選択をしました。私たちの原点ともいえる『aroma journey (アロマジャーニー) 』も、一旦販売をお休みさせていただき、来春を目標にオー・デ・コロンとして生まれ変わる予定です。

ーーー 現在向き合っている社会課題について教えてください。
現在、グリーディーと並行して、一般社団法人ワンエムイノベーションという別法人を立ち上げ、女性の働き方や生き方をエンパワーする各種プログラムを提供しています。
この活動を始めたきっかけは、前職時代に約200名以上の女性社員をマネジメントしていた経験にあります。彼女たちは、家庭や地域の事業、制度の壁など様々な理由から、やりたいことがあっても、小さく諦めるケースも多く、それがすごく「もったいない」と感じていました。
特に地方では、職種が限られることも多く、キャリアの選択肢が狭くなります。私も実際、東京と仙台の2拠点生活をしていたことがありますが、やはり情報格差・機会格差があると感じました。首都圏、もしくは東京での生活の中では、帰り道にふらっとイベントに立ち寄ったり、最前線で活躍される方々とつながる機会が自然にあるのに、地方ではその“出会いの機会”すら手に入りにくい。そうした背景から、「地方でも女性がクリエイティブに働ける環境を作りたい」ということに強く関心を持つようになりました。
私が目指している「クリエイティブに働ける環境」とは、単にデザインや企画といった分かりやすい仕事だけを指すわけではありません。例えば事務や製造、オペレーション職だとしても、「ここをこう工夫したらもっと良くなるのではないか」と、日々の業務に創造性や主体性を持ち込むことで、自分の頭で考えながら働くことができます。そうした“クリエイティビティ”を発揮できる環境こそが、地方で働く女性たちにとっても必要だと感じています。
例えば、日本マイクロソフト株式会社と女性支援団体との協働により、挑戦する意志を持ったシングルマザーやジェンダーギャップの影響を受けやすい地方在住の女性たちに、ICTスキルを学ぶ機会を提供するプログラムを、NPO法人シングルマザーズシスターフッド(代表理事吉岡マコ氏)と連携し開発しました。また、さらにここ数年は、LinkedIn(リンクトイン)の協賛により「土曜日の学び舎」というウェルビーイングプログラムを展開し、女性の自分らしい生き方・働き方について考えるきっかけを提供しています。
ーーー 今後の展望についてぜひ聞かせてください。
「天然回帰」というブランドは今はまだ「宮城で作って、宮城で売る」が中心ですが、将来的には「東北で作ったものが全国・グローバルでも通用する」という形にしていきたいと考えています。
「天然回帰」ブランドのモデルが確立をし、全国の仲間と連携することで、それぞれの地域で同じように事業を起こしていくことができます。各地の同じ志をもった仲間と連携することで、大きな力になると思っています。地域ごとの特色や想いが活きる形で「みんなで全国に通用するブランドを一緒に育てよう」という世界観をつくりたいです。
また、日頃スタッフには「商品を届けるということは、夢を届けることでもある」と伝えています。私自身は「お客様には夢を、スタッフには誇りを」持ってもらえるようなモノづくりをしたいという気持ちを大切にしています。香りの会社としての側面だけでなく、「女性が経験を積み、クリエイティビティを発揮できる場でありたい」という思いもあります。そのため、会社としても成長しながら、そうした若い女性たちを育てていける存在になっていきたいと思っています。
ーーー ご自身は東北学院大学に在学中、どんな学生でしたか?
当時は、バブル期の学生だったこともあり、正直なところ勉強もあまりせず、将来の夢は「専業主婦」でした。そんな価値観にとらわれていた気がします。今思えばもっと主体的だったらよかったなと思う反面、時代背景もあったのかなとも感じます。
私自身は、新卒で入った会社でも正直「すぐ結婚して辞めるだろうな」と思っていたので、当然失敗も多かったです。でも、最近スタッフと話していて、「辛かったことや痛みを伴った経験からしか、本当の学びって得られないよね」という話になりました。若いうちはリカバリーが効く分、いっぱい失敗して、経験を積むことが大事だなと改めて感じています。失敗を恐れずに若いうちにどんどん経験を重ねてほしいですね。
ーーー 将来スタートアップを目指したい学生に対してのメッセージをお願いします。
私は、「好きなことはとりあえずやってみる」「悩んだらやってみる」という姿勢を大切にしています。私自身も、もともとは趣味でアロマの勉強をしたり、自宅で手作り石けんを作ってワークショップを開いたりしていただけでした。まさかそれが仕事になるとは思っていませんでしたし、本当に趣味から始まったものです。でも、自分がやってきた経験と好きな事が繋がって仕事になっていることは、とても幸せなことだったと感じています。
だからこそ、学生の皆さんにも、何か少しでも興味を持ったことがあれば、まずは一歩踏み出してみてほしいと思います。例えば、気になるイベントがあれば、深く考える前にまず参加してみる。自分のアンテナに引っかかる感覚というのは、過去の経験や内なる関心からくるものです。全く興味のないものには、そもそも反応しないはず。ですので、少しでも心が動いたら行動に移してみてください。やってみて「違うな」と思えば、やめればいいんです。やらないと分からないことって、本当に多いですからね。
そして、チャンスが訪れた時、「自分にはできないかもしれない」と決めつけてしまったり、謙遜したり、遠慮することなく、「まずは一度やってみよう」という気持ちで挑戦してみることが大切です。できるかどうかは、やってみて初めて分かること。最初から能力の有無で判断せず、今の自分にできることから少しずつ始めてみればいいと思います。
未来を切り開くためには、まず自分自身の内なる声に耳を傾け、思い込みを捨てること。好奇心と情熱を持って一歩踏み出す勇気を持つこと。それが、新たな可能性へと繋がる道だと私は信じています。